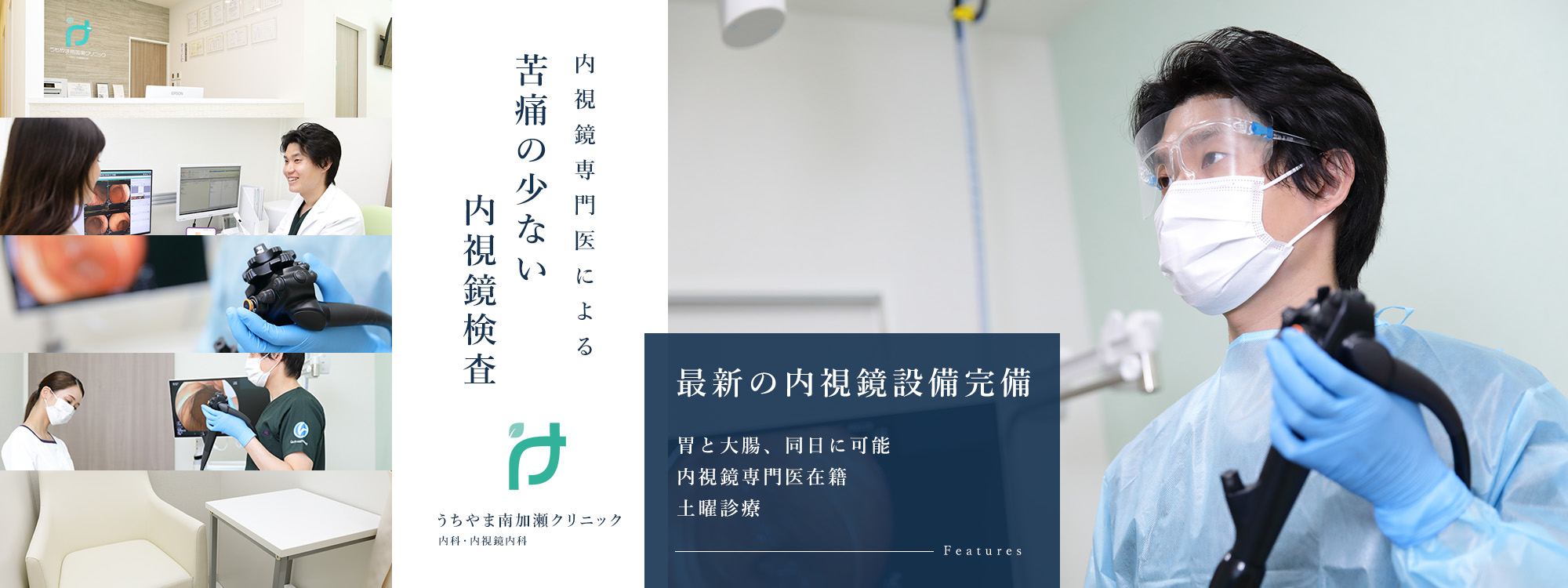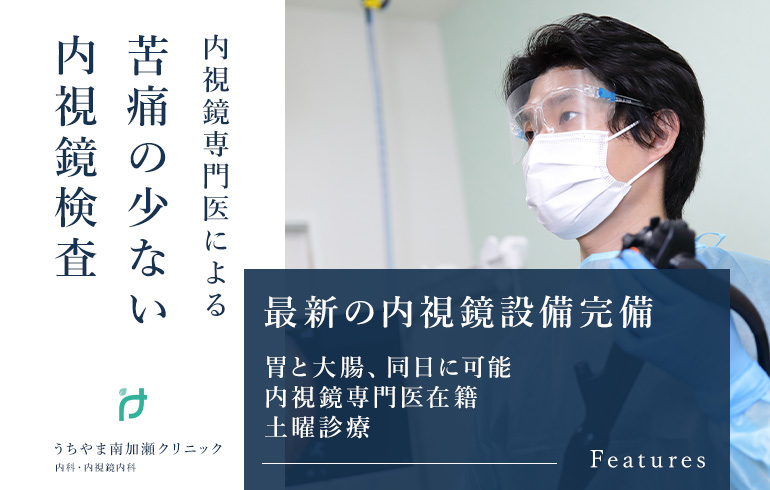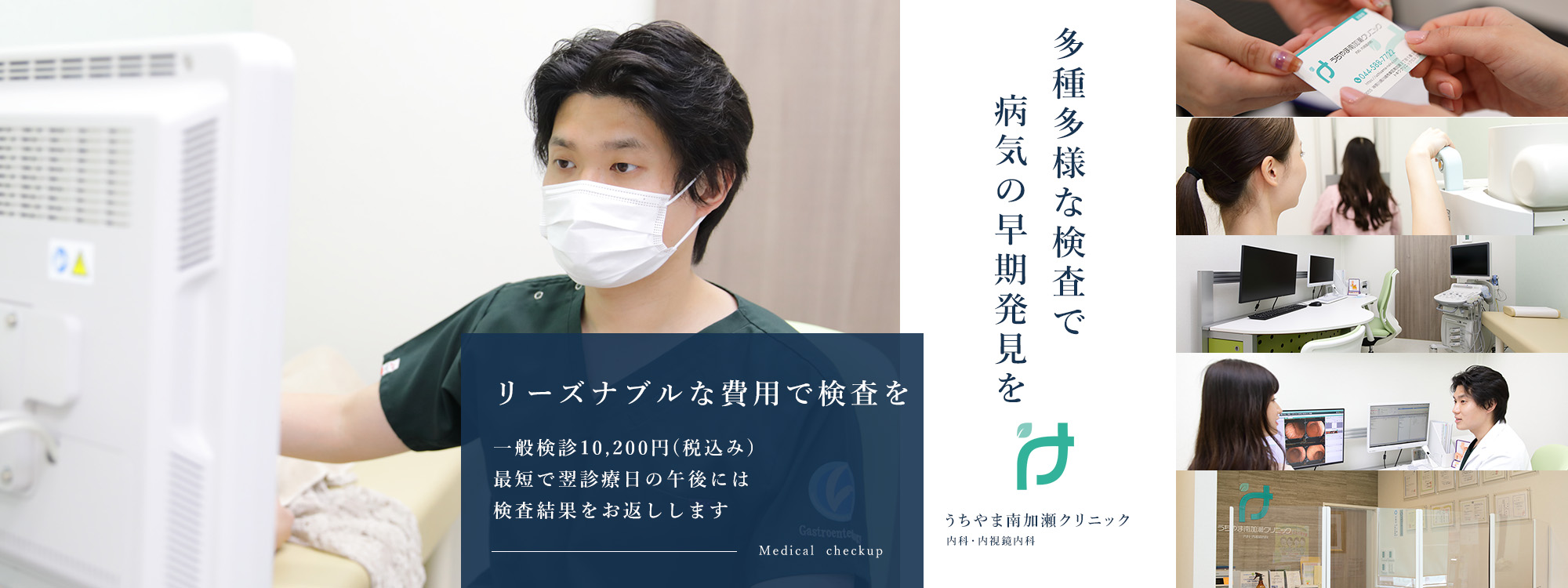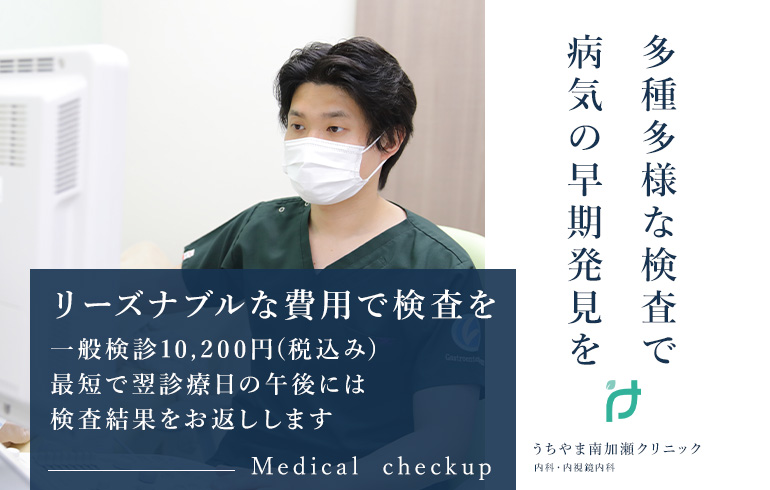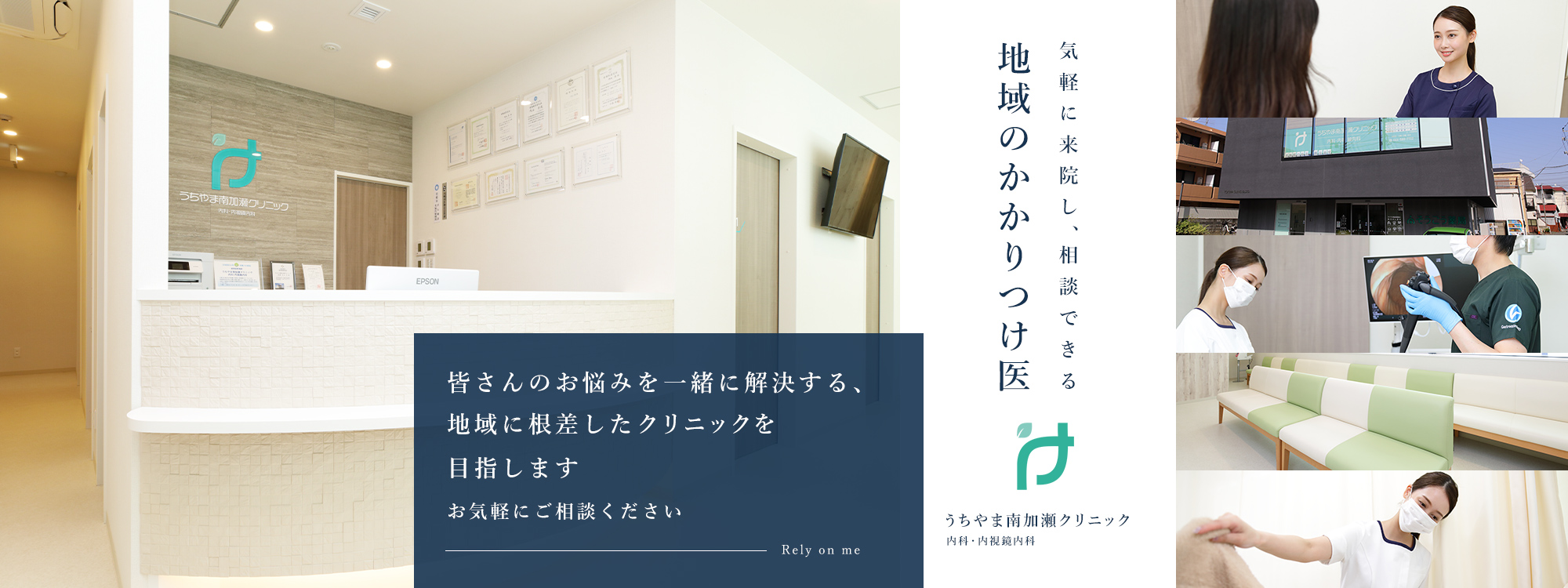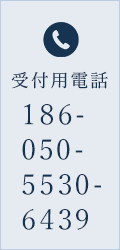インフルエンザと風邪は違う
 インフルエンザは、ウイルスによって引き起こされる感染症です。 風邪の多くは咳やくしゃみ、鼻水、のどの痛みなどの症状がゆるやかに現れ、発熱も軽度(微熱の場合だと37℃前後で、高くても38℃未満)です。発症後の経過もゆっくりで、徐々に回復していきます。 しかしインフルエンザにかかってしまうと、普通の風邪と同じような症状(咳、鼻水、のどの痛み)に加え、高熱(38℃以上)や、関節・筋肉痛、全身のだるさ(倦怠感)なども発生します。
インフルエンザは、ウイルスによって引き起こされる感染症です。 風邪の多くは咳やくしゃみ、鼻水、のどの痛みなどの症状がゆるやかに現れ、発熱も軽度(微熱の場合だと37℃前後で、高くても38℃未満)です。発症後の経過もゆっくりで、徐々に回復していきます。 しかしインフルエンザにかかってしまうと、普通の風邪と同じような症状(咳、鼻水、のどの痛み)に加え、高熱(38℃以上)や、関節・筋肉痛、全身のだるさ(倦怠感)なども発生します。
加えて、腹痛や吐き気などの消化器症状などを発症する傾向もあります。 また、インフルエンザは合併症にも気を付けていく必要があります。 特に高齢層の方(65歳以上)や慢性疾患や糖尿病などを抱えている方、妊婦の方、5歳未満の幼児がインフルエンザにかかってしまうと、ウイルス性肺炎やインフルエンザ脳炎などの発症リスクが高くなってしまいます。生死にかかわるので、気を付けて対策してください。
インフルエンザの流行について

「極力早めに予防接種を受けたい」と考える方も多いかと思いますが、予防接種の効果期間は「約5ヶ月」だと言われています。そのため、毎年ピークになる1月~2月に予防効果を発揮させるには、「10月中旬~11月下旬まで」に予防接種を済ませておくことが大事です。
予防接種の受診は極力「10月中旬~11月下旬まで」に済ませておき、手洗いやうがい、栄養バランスの良い食習慣、睡眠時間の確保など、免疫力向上とインフルエンザ予防対策をしっかり心がけていきましょう。
インフルエンザの潜伏期間
インフルエンザウイルスの潜伏期間は1~3日ほどです。体調や体質、年齢によって異なりますが、潜伏期間の平均は2日程度になります。 インフルエンザウイルスは1日で一気に増殖するので、すぐに発症することも多いです。
症状が目立たない潜伏期間中に、他人へうつしてしまうこともあります。
インフルエンザの感染経路
インフルエンザを日常的に予防するために、どのような経緯でインフルエンザ感染が起きてしまうのかを把握しておきましょう。 インフルエンザの感染経路は二種類あり、「飛沫感染」と「接触感染」です。
飛沫感染

飛沫感染

具体的な予防法
インフルエンザの感染・感染拡大を防ぐためには、飛沫感染・接触感染を徹底的に対策していくことが重要です。 普段から咳エチケットをこころがけていき、「かからない」「他人へうつさない」を心がけていきましょう。
手洗いをしっかりする

出先でこまめな手洗いが難しい場合は「アルコール消毒液」や「消毒用のウェットティッシュ」など、すぐに使うことができる消毒用品を持ち歩きましょう。
外出時のマスク着用+咳エチケット
マスクを着用する目的は「人にうつさないこと」です。 現在のところウイルスを100%防げるマスクは存在していないので、残念ながら完全予防は難しいです。しかしマスクを着用することで、ある程度の防御ができます。
また、のどが乾燥してしまうと粘膜の防御機能が低下してしまい、感染リスクが高くなってしまいます。マスクは口腔内の保湿にも役に立つので、インフルエンザの予防対策に有効です。
咳エチケットの徹底

そのため、インフルエンザに感染していることに感染者本人や周りが自覚していない間に、感染拡大が起きてしまう恐れがあります。 インフルエンザの感染拡大を防ぐには、ひとりひとりがマスク着用や咳エチケットを守ることが大事です。些細なことですが、それらを守る人が増えるほどインフルエンザの感染リスクも減っていきます。
マスク着用時の注意
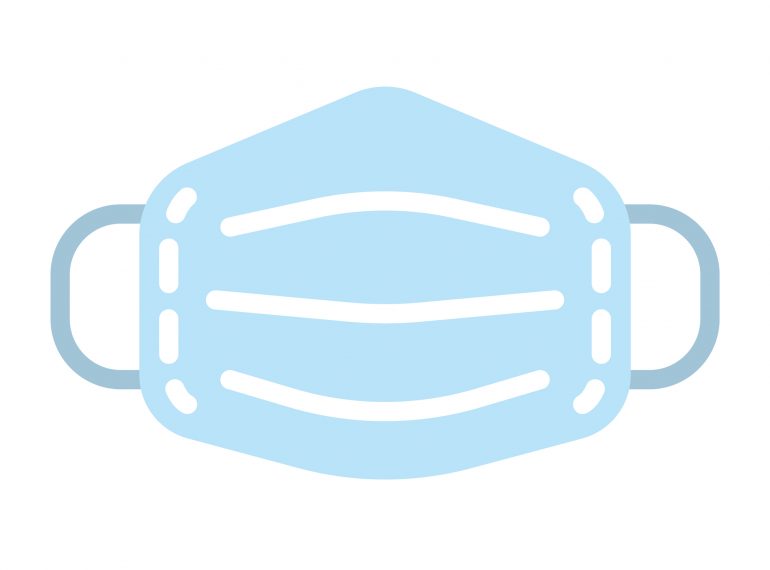
着用していたマスクを外すときに、マスクの表面(外側)に付いているウイルスに触れてしまうことで、口や鼻の粘膜にウイルスが入ってしまう恐れがあります。また、ウイルスが付いた手でマスクの内側に触れてしまうことによって、接触感染のリスクが上昇してしまうこともあります。
マスクで接触感染が起きないよう、マスクを外した後・着用する前は、手洗いとアルコール消毒を心がけましょう。
十分な栄養と睡眠
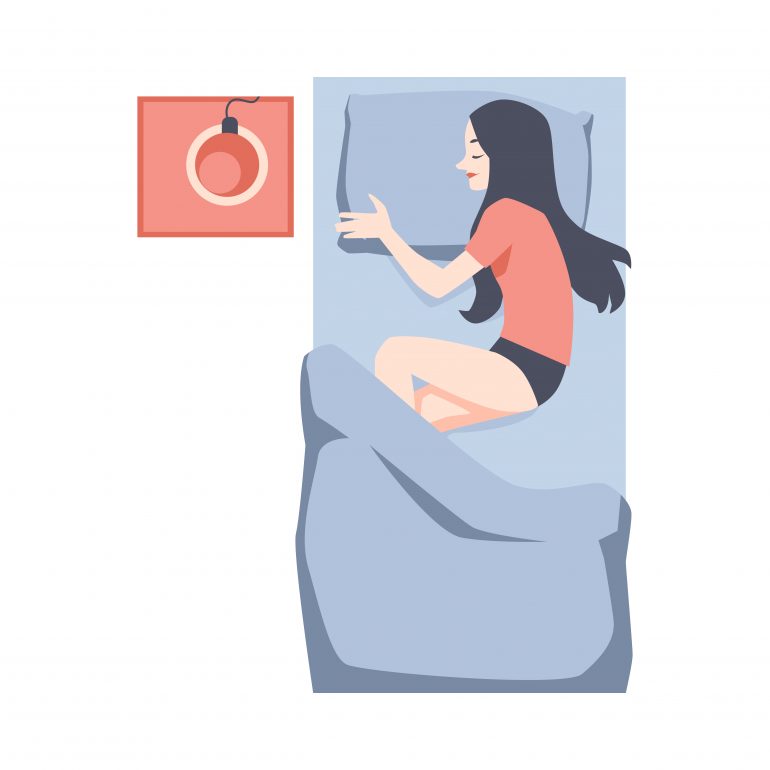
免疫力を高める食事
免疫力向上において、腸内環境を整えることも大事です。納豆やヨーグルトなどの発酵食品をこまめに摂取し、免疫力を高めていきましょう。
湿度を保ち、乾燥させない
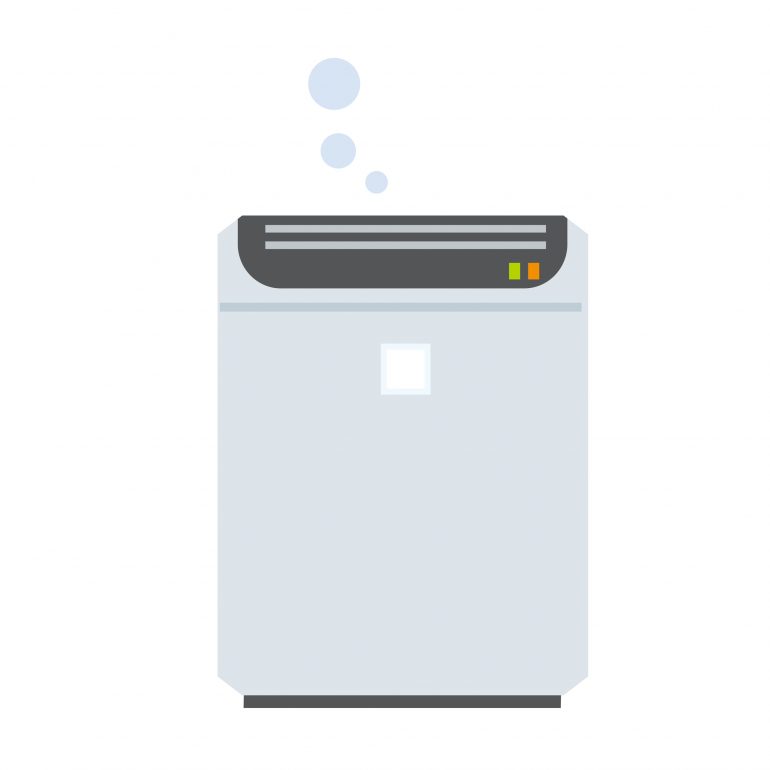
就寝時にもマスクを着用すると口腔内の乾燥対策になるので、着用しての睡眠もお勧めします(睡眠の妨げになってしまう場合は無理せず外しましょう)。 またインフルエンザウイルスは、高温多湿な環境下では生存できなくなります。そのため、室温を20~25度をキープするよう心がけてください。
人混みの多い場所・繁華街への外出を控える

インフルエンザの予防接種をうける
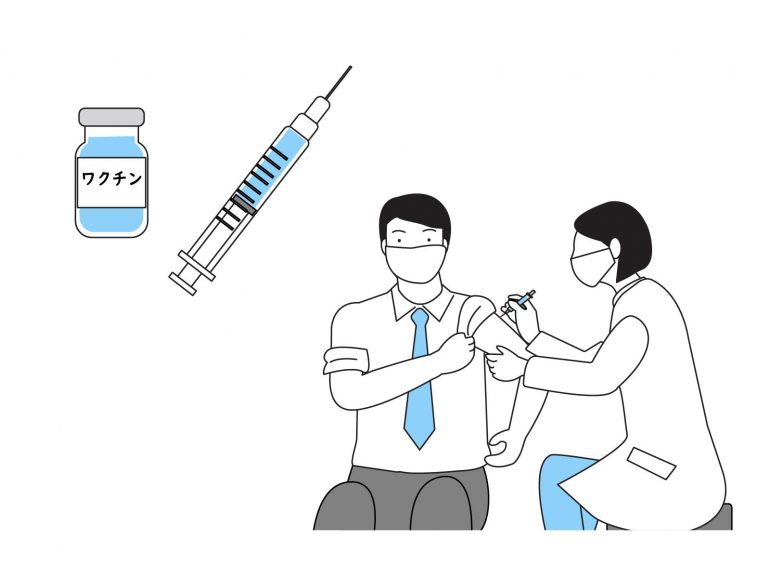
インフルエンザワクチンを接種することは、発症リスクを抑えるだけではなく、重症化リスクの軽減にも有効です。ぜひ、ワクチンの接種を毎年受けましょう。