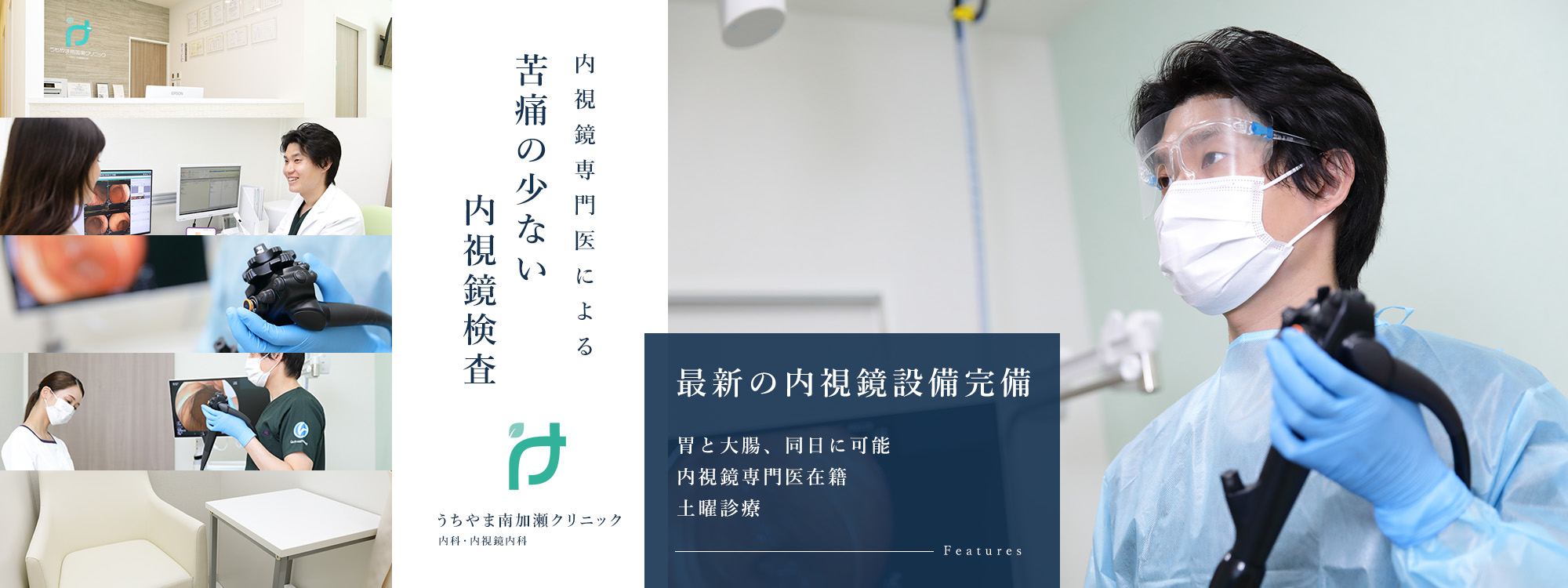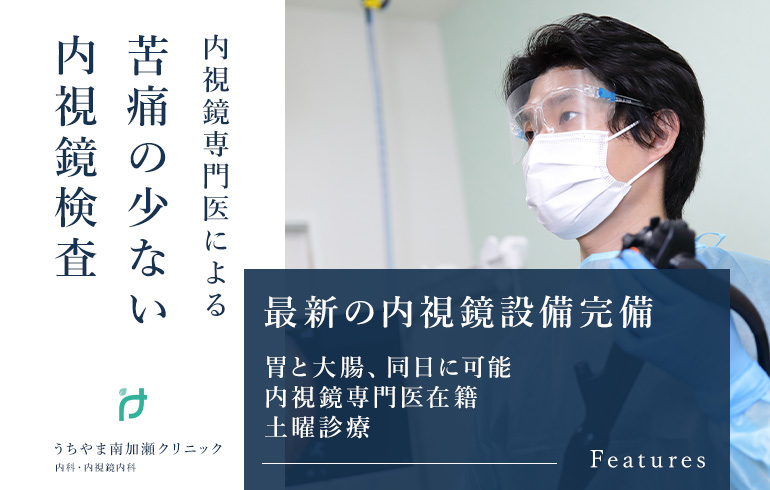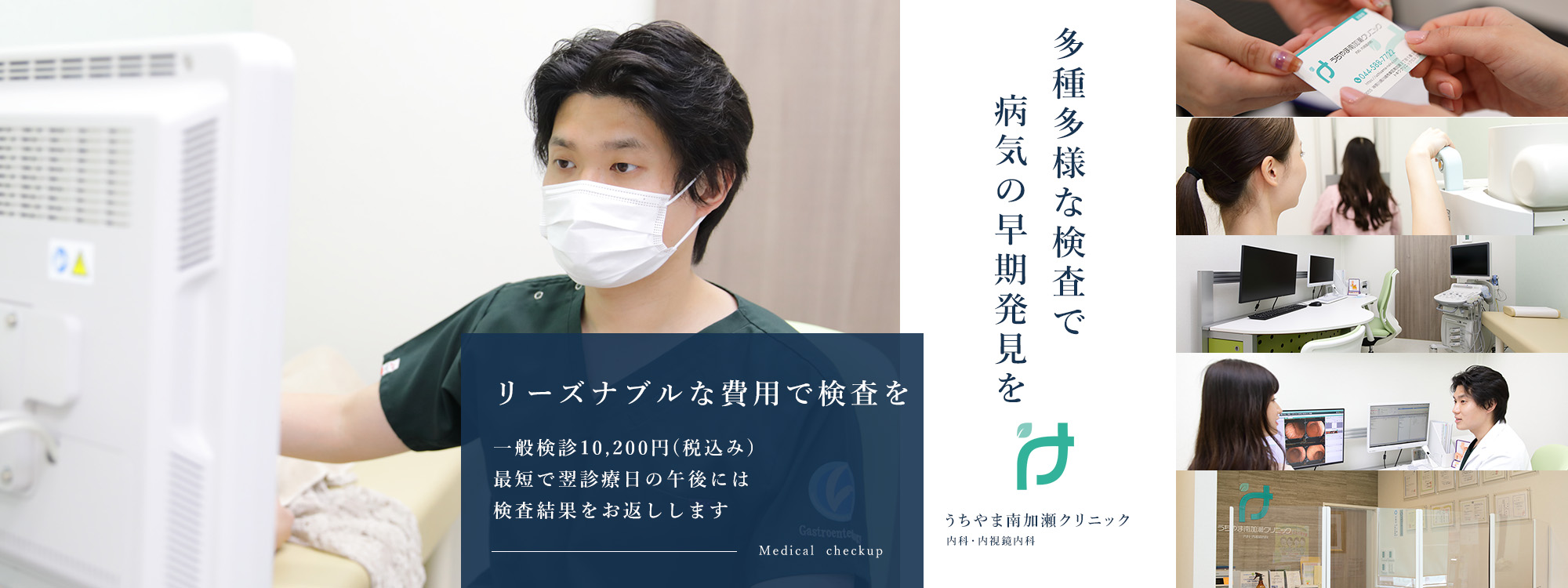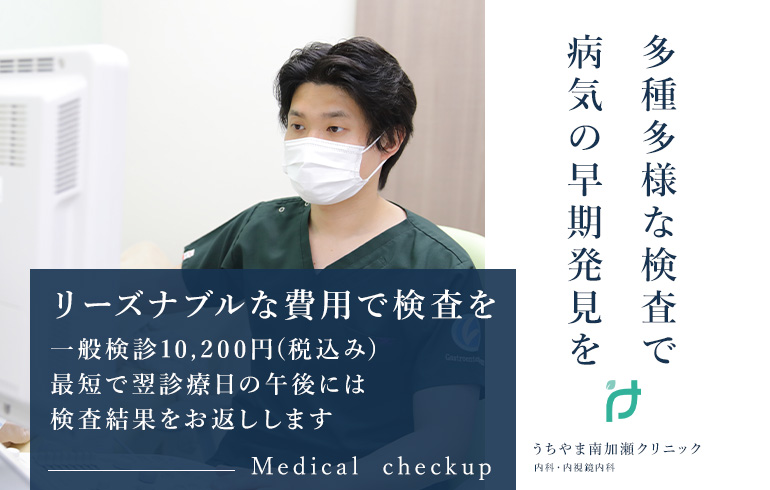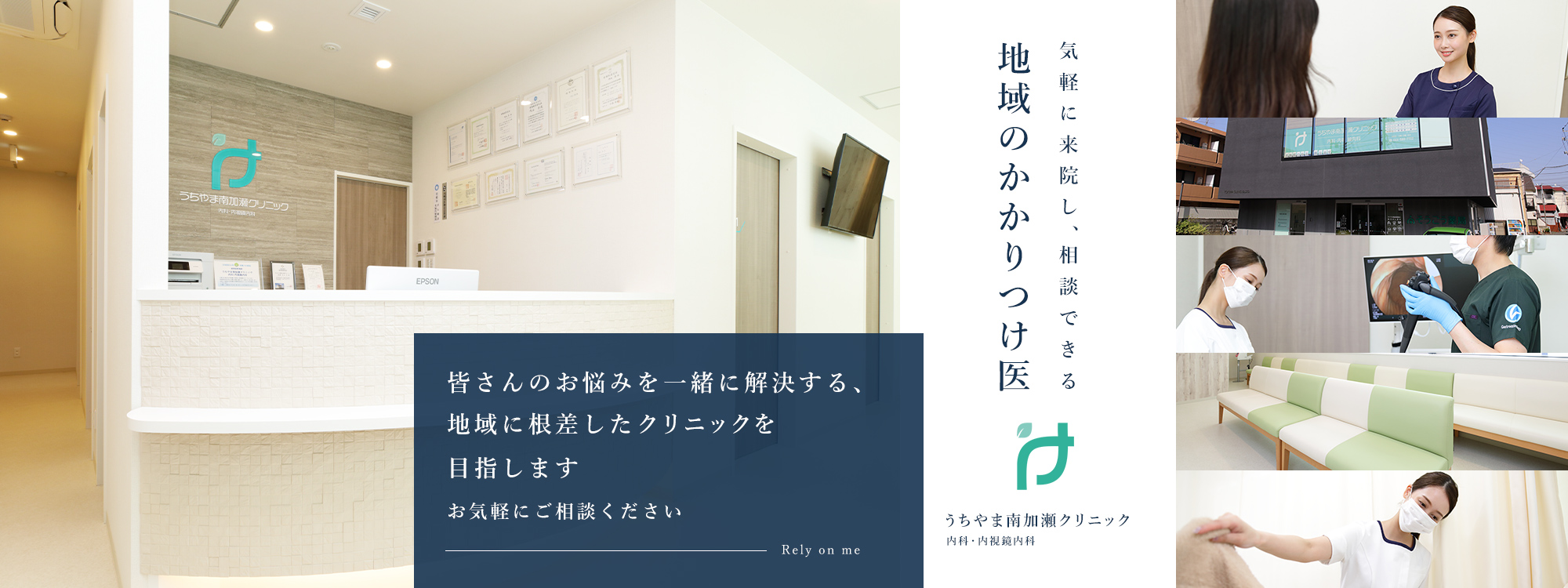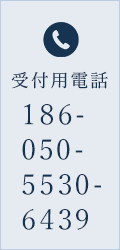胃炎とは

しかし強い刺激によって粘液のバリア機能の限界を超えてしまうと、粘膜はダメージを受けてしまい、そこから炎症が起きてしまいます。 また、胃の消化機能は自律神経によって機能しています。そのため、自律神経が不安やストレスなどによって乱れてしまうと、防御機能が落ちやすくなります。それによって胃に炎症や痛みが起きてしまうケースもあります。
軽度の胃炎で発生するのは、粘膜表面のただれ(びらん)です。炎症が慢性化してしまうと回復力が低下し、防御や修復の役割を持った粘液の分泌が減少してしまい、炎症がますますひどくなります。ダメージが深刻になると胃潰瘍の発症リスクが高くなってしまいます。
症状
胃疾患はどのような疾患でも、似たような症状が現れやすいです。そのため、痛みが目立たない状態でも、深刻な疾患にかかっている恐れがあります。そのため、胃周辺で気になる症状があって悩んでいる際は、消化器系の病院を受診して、疾患を特定していきましょう。何らかの疾患がないと分かるだけでも安心できます。
急性胃炎

胃やみぞおち辺りの痛みやお腹の張り、違和感、むかつき、嘔吐などの症状が急に現れます。重症化してしまうと、吐血・下血なども起きてしまいます。
慢性胃炎

しかし、慢性的な胃粘膜の炎症が起きても、ほとんど症状を起こさず、無自覚のまま病状が進行してしまう恐れがあります。
胃炎の原因
急性胃炎

慢性胃炎

とくにピロリ菌検査で陽性が出た方は、速やかに除菌治療を受けましょう。 ピロリ菌の感染は幼少期の衛生環境によって左右されやすく、とくにピロリ菌に感染している成人から乳幼児への口移しが原因で引き起こされるともいわれています。衛生状態が改善した現在の日本では、感染者は減少してきています。しかし、先進国の中では感染率が高い傾向にあります。 ピロリ菌の除菌治療は、炎症や潰瘍の再発・発症リスクを抑えるために重要です。そして、次世代への感染リスクを抑えることにおいても大事です。
胃炎の検査
急性胃炎

慢性胃炎

また、検査中に胃炎が発見された場合は、組織を採取してピロリ菌感染の疑いがないかを調べる検査も実施可能です。 萎縮性胃炎に罹っている場合、放置してしまうと胃壁が薄くなり血管透見像(血管が透けて見えること)が起きてしまい、胃がんの発症リスクが高くなってしまいます。
萎縮自体は解消できないため、早期発見・早期治療はとても大事です。胃の症状がなかなか治らないようでしたら速やかに消化器専門医を受診して、胃内視鏡検査で疾患を特定していきましょう。
治療
急性胃炎・慢性胃炎にかかわらず、薬物療法と生活習慣の改善を行っていく必要があります。また、現在服用している薬の副作用がひどい場合は、処方を変えることで改善するケースもあります。また、ピロリ菌感染検査で陽性反応が出た方には、除菌治療を推奨します。
薬物療法

しかし、市販薬などでごまかしているうちに、胃がんの症状が進行してしまうこともあります。胃の症状がなかなか治らなくてお困りの場合はぜひ受診して、適切な治療を受けてください。
ピロリ菌の除菌治療
慢性胃炎のほとんどは、ピロリ菌の感染が原因です。炎症を慢性化させないため、そして胃がんの発症リスクが高くなる萎縮性胃炎を発症させないためにも、ピロリ菌感染の検査を行いましょう。陽性反応が出た方は、早急に除菌治療を行いましょう。 除菌治療は成功しない可能性もゼロではありません。しかし、その場合は処方する薬を変更して、2回目の除菌治療を行っていきますのでご安心ください。2回の除菌治療を受けた場合、その成功率は97~98%だといわれています。除菌に成功することで、胃炎や胃潰瘍の重症化・再発リスクはかなり低くなります。
生活習慣の改善
胃酸分泌が過剰になると炎症リスクが高くなってしまうので、胃酸分泌を促す飲食物は控えましょう。暴飲暴食をやめて禁酒を心がけていくだけではなく、コーヒーや濃い緑茶・抹茶などカフェインが多く含まれているもの、唐辛子などの刺激物、油が多い食事も控えてください。ストレスや精神的な要素などが原因で発症しやすい方には、規則正しい生活、十分な睡眠や休息の確保と、ストレスの解消などの指導も行っていきます。